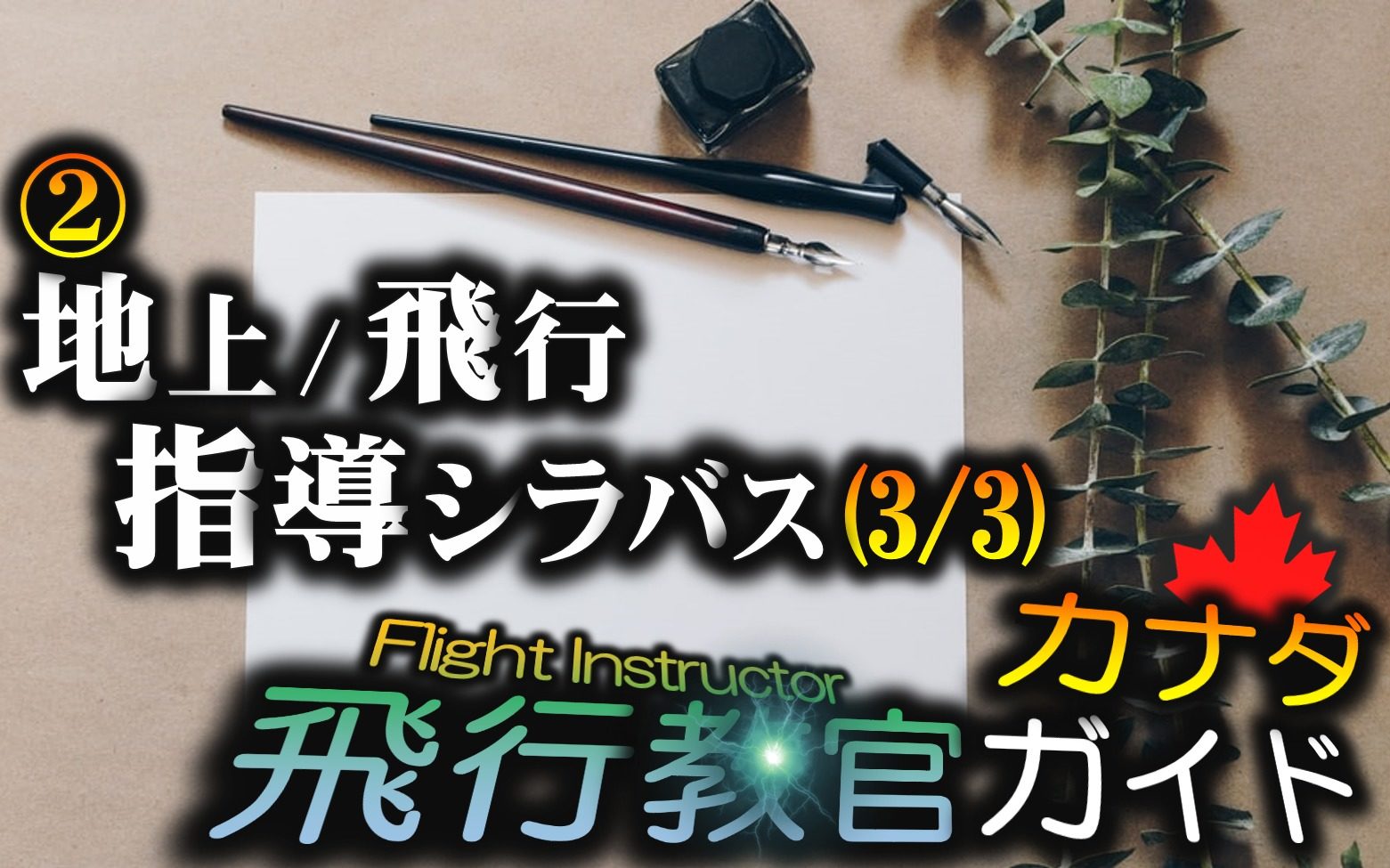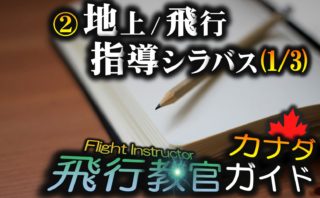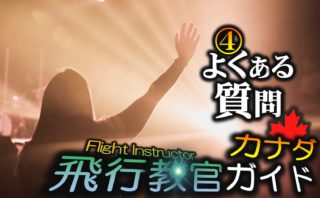第2部 地上/飛行指導シラバス (3/3)
本記事は、4部で構成される飛行教官ガイドの第2部に基づくものです。
第2部は量が多いため、前編(課目1~15)と中編(課目16~23)と後編(課目24~29)に分割しています。
第1部「学習と学習要素」
第2部「地上/飛行指導シラバス」
第3部「訓練計画の作成」
第4部「よくある質問」
課目24:計器飛行

全計器使用
【全計器飛行】姿勢と運動
次のような事項について計器を参照して実施させるよう指導
- 機体の通常運用時の姿勢範囲
- 所望の姿勢を確立し維持するために必要な飛行と制御法
- ヨーイングの制御法
- 計器により取得した情報を外部参照に関連付ける能力は、計器飛行法の基礎となる
- 計器飛行指導を実施前に次のような影響について復習
- 感覚の制限 (視覚 / 前庭神経 / 運動感覚)
- 方向感覚喪失 (視覚的錯覚 / 前庭神経錯覚)
- 疲労 (急性 / 慢性 / 技量への影響)
- 風邪と副鼻腔炎
- ストレスや感情起伏
- 不規則な食生活
- アルコールと二日酔い
- 薬品 (処方薬 / 市販薬 / 麻酔薬)
- ドラッグ
- 低酸素症と過呼吸
- 一酸化炭素
- 献血
- コクピット内騒音 / 灯火 / 振動
- 計器飛行中に各種錯覚が予想されることと、それらに対処する方法について説明
- 計器飛行指導の実施前に次のような用語について復習
- ピトー管
- 静圧
- 動圧
- 位置誤差
- ジャイロ・プリセッション
- ジャイロ剛性
- 指示対気速度 (IAS)
- 真対気速度 (TAS)
- 較正対気速度 (CAS)
- 実高度
- 指示高度
- 各飛行計器の機能と基本的な機械操作について説明
- 各種操作 / 各種制限 / 誤差 / 計器の使用可否点検の情報源について強調
- 制御や性能計器に関連する考え方について説明し、次の項目について具体的に説明
- スキャンの目的
- 選定方位スキャン法
- スキャン速度
- 計器不具合の発見
- よくあるスキャニングの誤り
- 次の姿勢に関する計器表示について説明
- 巡航
- 機首上げ
- 機首下げ
- 旋回
- 次の運動に関する計器表示について説明
- ピッチング
- ローリング
- ヨーイング
- 次の事項について説明
- 運動を生じさせる、もしくは機体を所望の姿勢にするために必要な制御入力は、有視界飛行で使用するものと同様
- 姿勢と出力を確立するために制御計器を、速度 / 昇降率 / その他所望の性能を確認するためにパフォーマンス計器を参照
- 変更を行うのには制御計器を使用し、パフォーマンス計器は速度 / 昇降率 / その他の性能情報を確認するために使用
- 円滑な制御力を使用し、細かな修正を行い、結果を待つ
- 増減速 / 上昇降下 / レベルオフの際に、所望の速度や高度に到達するために出力や姿勢を変更する必要性を予測
- トリムの正しい使用は、制御の維持に不可欠
- 飛行中は計器表示に集中するため、他機の状況について注意深く監視することに気を取られる可能性があるため、常時厳格な見張りを維持
教官が学生の代わりに他機の飛行状況を監視していることを伝え安心させるため、学生に「ALL CLEAR LEFT (OR RIGHT) ?」と確認させ、確認を待ってから旋回を開始 - この最初の計器飛行訓練部分は、以降の訓練の基礎事項をカバーしているため、この訓練についてはすべての原則を注意深く説明するよう努力
- 最初の数回の訓練では安定した気流で実施
- 姿勢と運動の全体的な上空での教示については視界制限装置を使用せずに実施することで、学生は訓練内容に集中可能
最初の教示の実施後、学生は計器だけを参照して飛行訓練が可能 - 学生が計器を参照して飛行している間は、最初は訓練時間は短めに実施し、進捗に応じて徐々に長めに設定
- 機体制御に疑問がある場合には、ラダーで直進を維持し、エルロンで翼を水平にすることを強調
- 上昇降下 / 旋回時には、参照するのが外部の視覚的なのか計器表示なのかによらず同様の制御入力が必要であるように、計器飛行訓練を目視で行う同等の訓練と関連付け
- 姿勢計の見方として、尾翼に座って機体の翼を前に見ているように学生に指導
- 訓練機で可能であれば、旋回釣合計と旋回傾斜計の違いについて教示
- 部分的計器搭載機を使用した自家用操縦士免許の取得訓練も許可されているが、飛行実技検定では全計器搭載機と同基準で実施することを指導
外部参照を維持しつつ次のような事項を実施
- 水平直線飛行を確立
- 通常巡航で水平飛行できるよう姿勢計のミニチュア機を調整
- 水平線に対する実際の機体姿勢と姿勢計上の表示との相違点について教示
- パフォーマンス計器に常時表示される情報ついて指導
- 外部情報を参照しつつ、ピッチング動作の視覚的兆候と計器表示について比較
- 姿勢計にあわせて機首上げ姿勢とし、姿勢計上の水平線表示と実際の水平線の相違点について指導
- 姿勢計の機首上げ表示と実際の機体の機首位置について比較
- 姿勢計のピッチスケールについて指導
- パフォーマンス計器の表示について指導し、巡航姿勢の表示と比較
- 機首上げピッチ変化量と、速度計 / 昇降計 / 高度計が示す変化量との関係について教示
- 機首上げ姿勢の通常範囲について教示
- 昇降計の瞬間的なラグについて指導し、急激なピッチ変化とラグ / 反転との関係について教示
- 巡航姿勢に復帰
- 姿勢計に合わせて機体を機首下げ姿勢にし、実際の水平線と姿勢計上の水平線との相違点について指導
- 姿勢計の機首下げ表示と実際の機体の機首位置について比較
- 姿勢計のピッチスケールについて指摘
- パフォーマンス計器の表示について指摘し、巡航姿勢の表示について比較
- 機首下げのピッチ変化量と、速度計 / 昇降計 / 高度計に示される変化量との関係について教示
- 機首下げ姿勢の通常の範囲について教示
- 昇降計の瞬間的なラグについて指摘し、急激なピッチ変化によるラグや反転の関係について教示
- 巡航姿勢に復帰
- 計器を参考にして、機首上げ / 機首下げの姿勢、巡航姿勢の訓練機会を学生に付与
- ローリング動作において、外部の視覚的兆候と計器表示について比較
- 機体をバンク姿勢とし、実際の水平線と姿勢計上の水平線の相違点について指導
- 姿勢計がバンクを直接示す方法について指導
- 姿勢計のバンクスケールについて指摘
- 穏旋回 / 中程度旋回に対するバンク姿勢範囲について教示
- 方位計と旋回傾斜計の旋回表示について指導
- 機体旋回中の旋回傾斜計の表示について教示
- バンク角と方位変化率の関係について指導し、方位計がバンク角を間接的に表示していることを説明
- 旋回針がヨーイングに反応することを教示し、翼を水平に維持しラダーでヨーイングされている際の旋回針の表示と、バンク中にラダーでヨーイングが防止されている際の旋回針の表示について指導
- ボールが中央にある場合、バンク角と旋回率の調和がとれていることを指導
- ボールが中心からズレた位置にある場合、対応する翼が調和のとれた旋回に必要なレートよりも低いことについて指導
- 旋回針がバンク角の間接的な表示として使用できるのはボールが中央にある場合のみであることを強調
- 計器を参照しつつ、学生に左右の各種バンク姿勢での訓練機会を付与
- ヨーイング運動を視覚的と計器表示の両方について比較
- 旋回傾斜計がヨーイングを直接示していることを指導
- 旋回に必要なヨーイング量は、適切なバンク角を選定することにより生ずることを指導
- 「ラダーで旋回針の動きを制御することで、その起源に関係なくパイロットの意思に反した影響を与える任意のヨー」と定義されるアドバースヨーの制御法について教示
- 計器を参照しつつ出力変化 / 旋回 / 上昇降下時のヨーイング制御について学生に訓練機会を付与
【全計器飛行】水平直線飛行
- 計器を参照しつつ、次の飛行法について指導
- 直線飛行
- 水平飛行
- 各種速度での水平直線飛行
- 水平直線飛行により学ぶ飛行法は、計器飛行のほとんどの場面における基本となること
- 姿勢計上の翼の水平表示
- 旋回傾斜計のヨーイング表示
- 後流効果 / 非対称推力 / エルロン抗力などのヨーイングの予測
- マグコンパス自体とコンパスの精確な読み取り法に関連するエラー
- 次の方法を用いた直線飛行のための正しいスキャン法
- 姿勢計を参照して翼水平の姿勢を確立
- 方位計を頻繁に参照し、所望の方位の維持を確認
- 旋回傾斜計を時折参照し、翼の水平とヨーイングが発生していないことを確認
- 水平飛行における姿勢計の設定要領
- 姿勢計における小さなピッチ変化検知の重要性
- 翼が水平でないときのピッチ姿勢の決定法
- 機体の適切なトリミングの重要性
- 次の要領による水平飛行の正しいスキャン法
- 姿勢計を参照しながら巡航姿勢を確立
- 高度計を頻繁に参照し、指定高度の維持を確認
- 昇降計を時折参照し、上昇下降の傾向を感知
- 姿勢と出力の変更の必要性を確認するための高度計と速度計をクロスチェック法
- 次の事項について確認
- 高度は機首の上げ下げにより制御
- 速度は出力により制御
- 水平飛行で速度変更時は、姿勢と出力の両方を変更
- 水平直線飛行における正しいスキャン法を確認し、直線飛行と水平飛行とのスキャン法の組み合わせ法について説明
スキャニング法については次の要領を適用
- 姿勢計と回転計を使用し、所望の速度で水平直線飛行を確立
- 方位計 / 高度計 / 速度計を頻繁に参照し、機体が所望の速度で水平直線飛行していることを確認
- パフォーマンス計器を使用し、方位 / 高度 / 速度の誤差を検知
- マグコンパス / 回転計 / エンジン計器を時折確認
- 増減速時に入力が必要な制御について説明
- 経験則推奨 (略算式)
- 100RPMすなわち1インチのマニホールド圧力の出力変化で、速度は約5kt変化
- 細かな方位修正を行う場合に使用するバンク角は、変針に必要な角度を超えない
- 水平直線飛行については徹底的な教示を行い、学生訓練に十分な時間を確保
習得した技量は、その他ほとんどの計器飛行の場面で適用できるため、この課目の習熟は重要 - マグコンパスに関する詳細については、計器手順マニュアル (TP 2076E) の第2部を参照
- 速度変更しつつ水平直線飛行について指導する場合は、加速前に必要な出力設定を決定しておくなど、学生にはまず一定の高度を維持するためにどの情報が必要か、次にその情報を取得するために選択式ラジアルスキャン法をどう変えるかについて定義させるよう指導
- 水平飛行では、出力変化に伴うピッチ変化の可能性があるため、学生は所望の高度を維持するため高度計と姿勢計を頻繁に参照
その後、新たな速度に接近するにつれて速度情報はますます重要となり、所望速度の確立 / 出力の正確な設定 / トリミング完了までは、速度計を頻繁に参照
- 外部情報を参照し、通常巡航速度で水平直線飛行を確立
- スキャン法を簡単に確認し、計器だけを参照して学生に直線飛行させる
- ラダーで直進を維持する間、翼を水平に維持し、調和のとれた飛行を維持する必要があることを強調
- マグコンパスについて紹介し、次の事項について簡単に説明
- 増減速や旋回に関連する誤差
- 安定した気流や乱気流を飛行中のマグコンパスから方位計の設定法
- 機体が針路から逸脱した場合に必要に応じ修正を行い、指定針路に復帰
- 外部情報を参照し、通常巡航速度で水平直線飛行を確立
- 機体が安定後、姿勢計を調整
- 維持する針路を指定
- 水平飛行のスキャン法を確認し、計器のみを参照して必要に応じ姿勢の調整により高度を維持
- 細かな高度修正には小さなピッチの姿勢変化のみを使用するよう教示
- 機体の適切なトリミングの重要性について強調
- 学生が計器を参照している際に、次の手順による増速方法について教示
- 新たな速度に必要な出力まで増加
- 針路維持のためヨーイング制御
- 高度維持のため、必要に応じピッチ姿勢を調整
- 必要に応じトリム調整
- 減速の方法について、次のように教示
- 新たな速度に必要な出力まで減少
- 針路維持のためヨーイング制御
- 高度維持のために、必要に応じピッチ姿勢を調整
- 必要に応じトリム調整
- 学生に各種速度における水平直線飛行の訓練機会を付与
【全計器飛行】上昇
計器の参照を用いながら次の事項の実施について指導
- 指定速度で上昇を開始し維持
- 指定上昇率で上昇を開始し維持
- 上昇からのレベルオフ
- 最大の上昇性能を獲得するためには、特定の速度と上昇率で上昇できる能力が不可欠
- 次の事項について確認
- ヨーイング制御 / 非対称推力 / 後流の影響など予想されるラダーの要件について学生に質問
- 上昇開始 (姿勢⇒出力⇒トリム)
- レベルオフ (態度⇒出力⇒トリム)
- 次の事項について説明
- 最大上昇率速度で上昇できる機首上げピッチ姿勢
- 特定速度での上昇開始とそれを維持する際の正しいスキャン法
- 指定上昇率で上昇する際の正しいスキャン法
- 速度と上昇率を細かく修正するための小さな制御入力の使用
- 上昇からレベルオフする際の正しいスキャン法
- 上昇率に基づくレベルオフ時の見越し量の見積もり法
- 学生が次のような重要な質問に継続的に答えることを強調
- どのような情報が必要か?
- どの計器で必要な情報が得られるか?
- その情報は信頼できるか?
- 推奨経験則 (略算式)
- 1°のピッチ変化で、速度は約5kt変化し、上昇率は約100ft/m変化
- 100RPMすなわち1インチのマニホールド圧力の出力変化で、速度は約5kt変化し、上昇率は約100ft/m変化
- 上昇からレベルオフに移行する際、上昇率が500ft/mの場合は、目的高度到達の50ft前でレベルオフ操作を開始するなど、上昇率の10%の見越しを採用
- 一定の速度で上昇する際は、小さな姿勢変化で小さな修正を実施
- 学生が計器参照中に、次のような事項ついて教示
- 上昇に必要な概略の姿勢まで機首上げ
- 上昇出力設定まで出力増加
- 速度計と姿勢計をクロスチェックし、ピッチ調整の必要性を判断
- 姿勢計を参照しながら必要に応じて姿勢を調整し、速度計とクロスチェックして正しい上昇速度の達成を確認
- 必要に応じトリミング
- この運動全体での方位監視の必要性について強調
- 学生に一定速度で直進上昇の訓練機会を付与
- 学生が計器参照中に、次のような事項ついて教示
- 姿勢計を使用し、巡航姿勢に調整
- 高度計と方位計を頻繁にクロスチェックし、所望の高度と方位の維持を確認
- 機体が巡航速度に到達したら巡航出力を設定
- 必要に応じトリミング
- 機体の増速時に速度の注意深い監視の必要性を指摘
- 学生に定速上昇とレベルオフの訓練機会を付与
- 学生が計器参照中に、次のような事項について教示
- 所定の上昇率と速度で上昇するために必要な姿勢と出力設定を推定
- 姿勢と出力を調整し上昇を開始
- 速度計と姿勢計をクロスチェックし、ピッチ調整の必要性について判断
- 昇降計と姿勢計をクロスチェックし、出力調整の必要性について判断
- 必要に応じ姿勢と出力を調整
- 必要に応じトリミング
- 学生に定上昇率上昇とレベルオフについて訓練機会を付与
【全計器飛行】降下
計器の参照を用いながら次の事項の実施について指導
- 指定速度で降下を開始し維持
- 指定降下率で降下を開始し維持
- 降下からのレベルオフ
- 計器進入は通常、指定速度と降下率で実施することから、機体を効率的かつ安全に運航するためには、指定の速度と降下率で降下できる能力が不可欠
- 次の事項について確認
- 該当するコクピット点検
- 降下開始 (出力⇒姿勢⇒トリム)
- ヨーイング制御
- レベルオフ (出力⇒姿勢⇒トリム)
- 次の事項について説明
- 通常の降下のピッチ姿勢表示
- 指定速度で降下するための正しいスキャン法
- 指定降下率で降下するための正しいスキャン法
- 推奨経験則 (略算式) を使用し、指定降下率と速度で降下するための出力設定とピッチ姿勢を推定
- 速度と降下率に小さな修正を加えるための小さな制御入力の使用
- 降下率に基づいて、レベルオフのための見越し量を見積もる方法
- 推奨経験則 (略算式)
- 1°のピッチ変化で、速度は約5kt変化し、降下率は約100ft/m変化
- 100RPMすなわち1インチのマニホールド圧力の出力変化で、速度は約5kt変化し、降下率は約100ft/m変化
- 降下からレベルオフに移行する際、降下率が500ft/mの場合は、目的高度到達の50ft前でレベルオフ操作を開始するなど、降下率の10%の見越しを採用
- 学生が計器参照中、次のような事項について教示
- 該当するコクピット点検を完了
- 所望の出力設定まで下げ、通常巡航から降下を開始
- 所望の速度に近づくまで、巡航姿勢を維持
- ピッチ姿勢を調整し、所望の速度を維持
- 必要に応じトリミング
- 学生が計器参照中、次のような事項について教示
- レベルオフするための見越し量を見積もり
- 巡航姿勢を確立し、巡航出力を設定
- 姿勢計 / 高度計 / 方位計を頻繁にクロスチェックし、所望の高度と方位の維持を確認
- 必要に応じトリミング
- 加速時の速度について注意深く監視する必要性を指摘
- 学生に定速での降下とレベルオフについて訓練機会を付与
- 学生が計器参照中、次のような事項について教示
- 該当するコクピット点検を完了
- 所定の降下率と速度で降下するために必要な姿勢と出力設定を推定
- 所望の出力設定まで下げ、通常巡航から降下を開始
- 所望の速度に近づくまでは巡航姿勢を維持
- ピッチ姿勢を調整し、所望の速度を維持
- 所望の降下率を維持するよう出力を調整
- 必要に応じトリミング
- 姿勢計 / 速度計 / 昇降計を頻繁にクロスチェックし、機体が所望の速度と降下率で降下していることを確認
- 学生に定速下降とレベルオフの訓練機会を付与
【全計器飛行】旋回
計器を参照しつつ次の項目について指導
- 穏旋回 / 中程度旋回
- 1旋回率での旋回
- 選択方位への旋回
- 上昇降下旋回
- 急旋回
- 目的地への向首に必要な航法であり、計器飛行中に制御された旋回率で針路を変更する方法について熟知する必要
- 次の事項について説明
- 計器飛行中でも外部を参照し飛行する場合でも、同様の入力制御 / 旋回開始 / 回復手順や出力使用を実施
- エルロン抗力に起因するアドバースヨーの制御法
- バンク角は姿勢計のバンク指示計から判読
- 旋回中、姿勢計上のピッチ情報は機首位置を示すドットで表示
- 指定針路へロールアウトする際の正しい見越し量の見積もり法
- 1旋回率 / 速度 / バンク角の関係
- 機体がバンク姿勢に入る際、操縦桿にバックプッシャーをかける必要性を学生が予測
- 所望の旋回率となるバンク角を設定後、エルロンを使用してバンク角を修正し、旋回針の変動をラダーで制御
- 旋回における正しいスキャン法について説明
- 所望のバンク角で旋回中に、姿勢計を参照
- 旋回針をスキャンし、正しい旋回率の維持を確認
- 必要に応じバンク角を修正
- 旋回針を時折参照し、高度計 / 方位計 / 姿勢計をクロスチェック
- 姿勢計と旋回針をスキャンし、所定の旋回率を維持
- 方位計を頻繁にスキャンし、旋回からの回復を行うタイミングを確認
- ロールアウト方位に旋回が進むにしたがい、方位計を頻繁にスキャン
- 正しい見越しをもって翼を水平に戻しつつ姿勢計を参照
- 推奨経験則 (略算式)
- 旋回中に選定方位にロールアウトするには、30°バンク使用時は目的方位到達の15°前を見越しとするなど、バンク角の半分となる方位の前に到達した所でロールアウトを開始
- 細かな針路変更を行うには、小さなバンク角を使用するため、進路変更度数の半分のバンク角で十分
- 1旋回率を達成するための概略のバンク角は、次の公式で算出可
(KIAS / 10) + 7 = バンク角
- 旋回開始前に学生に「ALL CLEAR LEFT (OR RIGHT)」を確認させる
- 旋回の開始と終了は円滑で調和のとれた運動とすることと、外部参照で飛行する場合よりも遅い旋回率の使用が適当であることを強調
- 学生が中程度旋回に習熟した後にのみ、急旋回について指導
- 急旋回で学生が起こし得るエラーは次のとおり
- 旋回開始 (ロールイン) が速すぎて、スパイラル降下が発生
- 旋回開始時の出力増加が遅すぎて、速度低下が発生
- 旋回の開始 / 維持 / 回復時に正しいピッチ高度制御を維持できず、高度や速度エラーが発生
- 回復時 (ロールアウト) に必要な出力再設定しないため、翼が水平になった後に機体が上昇したり速度が増加
- 旋回開始 / 維持 / 回復時のスキャン法について確認
- 学生が計器参照中に、次のような事項について教示
- 穏旋回 / 中程度旋回を開始
- バンクにより旋回を維持し、ラダーによりアドバースヨーを制御
- 計器表示について指摘
- 旋回開始 / 維持 / 回復に必要なピッチ姿勢について指導
- バンク角と旋回率との関係について指導
- 正しい見越し方位を用いて直線飛行に戻り、ロールアウトを開始
- 学生に緩旋回 / 中程度旋回の訓練機会を付与
- 旋回開始 / 維持 / 回復のためのスキャン法について確認
- 学生が計器参照中に、次のような事項について教示
- 経験則 (略算式) を適用し、1旋回率での概略のバンク角を算出
- 標準旋回率旋回を開始
- 算出されたバンク角に到達後、正しい旋回率の確認のために旋回傾斜計を参照
- バンクにより旋回を維持し、ラダーによりアドバースヨーを制御
- 正しい見越し量を用いて直線飛行に復帰
- 学生に1旋回率旋回の訓練機会を付与
- 旋回開始 / 維持 / 回復のためのスキャン法について確認
- 学生が計器参照中に、次のような事項について教示
- 旋回を開始
- バンクにより旋回を維持し、ラダーによりアドバースヨーを制御
- 所望の方位に接近したら、方位計を頻繁にスキャン
- 正しい見越し量を用いて直線飛行に復帰
- 学生に指定方位への旋回について訓練機会を付与
- 旋回開始 / 維持 / 回復のためのスキャン法について確認
- 学生が計器参照中の穏 / 中程度バンクでの上昇旋回について教示
- 旋回を開始
- 旋回開始 / 維持 / 回復のために必要なピッチ姿勢について指導
- バンクにより旋回を維持し、ラダーによりアドバースヨーを制御
- 上昇 / 降下を維持しながら、旋回から復帰
- 学生に上昇降下旋回について訓練機会を付与
- 旋回開始 / 維持 / 回復のためのスキャン法について確認
- 学生が計器参照中に、次のような事項について教示
- 45°バンクを使用し急旋回を開始
- 旋回の開始 / 維持 / 回復中の姿勢計上のピッチ / バンク表示の変化について指摘
- バンクにより旋回を維持し、ラダーによりアドバースヨーを制御
- 旋回開始 / 回復中に必要な姿勢と出力変化について指導
- 計器を参照し、45°バンク旋回の開始 / 維持 / 回復について訓練機会を学生に付与
限定計器使用
【限定計器飛行】基本操縦
計器の一部を参照しつつ、次の事項について指導
- 水平直線飛行
- 上昇
- 降下
- 標準旋回率旋回
- 上昇降下旋回
- 計時旋回
- ジャイロ計器が壊れたり、使用不能になった場合でも、部分的計器のみを使用して飛行を継続できること
- ジャイロ計器の出力源が1つ故障が発生した場合でも、部分的計器を使用して飛行を継続できること
- 動作の基本原則と、旋回傾斜計の正しい使用法について確認
- 過剰制御を防ぐ必要性について強調
- 昇降計に関するラグがあることについて確認
- 姿勢や出力を変更した際に、増減速に時間がかかることについて説明
- スキャン法と、次の操作における入力 / 回復要領について説明
- 水平直線飛行
- 上昇
- 降下
- 標準旋回率旋回
- 一般的な標準旋回率旋回は毎秒3°の旋回で、小さな方位修正にはより遅い旋回率を使用することと、旋回はバンクにより生じ、不要なヨーイングはラダーにより制御することを説明
- 乱気流中で精確な方位や旋回率を維持して飛行するには、ラダーを使用して旋回針の位置を中立化することについて説明
- 計時旋回を実施する際の要領について次のように説明
- 計時を開始
- 旋回を開始
- 適時に計時を終了
- 旋回開始時と同等の制御力で翼を水平に回復
- 計器飛行要領マニュアル (TP 2076E) の第2部で概説されるマグコンパス原理について確認
- エラーが発生し始めたら、その変化量と速さは修正に必要な制御入力量と速度の決定に役立つ
- 学生が旋回率計と旋回傾斜計の操作と制限について完全に理解していることを確認
- 特に旋回開始と復帰時に、正しい制御の調整を確実に実施
- 計時旋回の訓練中、当初は30°の倍数となるような単純な方位変換を指示
- 学生が計器表示と機体に生じている状態との関連付けに苦労する場合には、まずは外部参照を使用して教示し、次に学生が計器を参照し反復
- 計時旋回において起こり得るエラーは次のとおり
- 旋回に必要な時間の算出が遅すぎ、学生が考えている間に方位変化
- 1旋回率の正確な旋回率を保持しない
- 開始方位や所要時間を失念
- ロールアウト後に翼を水平に維持しない
- 旋回精度の評価以前にコンパスが不安定のまま
- 部分的計器のみで訓練する場合も、自家用操縦士免許の飛行検定のためには全計器の精度範囲内における機体制御と操縦ができること
- 指示方位±15°以内
- 指示高度±200ft以内
- 指示速度±15kt以内
- バンク角が30°を超過しない
- 学生の計器参照時に、次のような事項について教示
- 水平直線飛行の確立
- ボールを中心にしつつエルロンで翼を水平に維持
- 旋回針を中心にしつつラダーで直進を維持
- マグコンパスを参照し、必要な方位の維持を確認
- 針路のズレの修正法について教示
- 水平飛行を維持するために必要な制御入力法とスキャン法について教示
- 高度誤差の修正法について教示
- 各種速度で水平直線飛行について教示し訓練機会を付与
- 学生が計器参照中、次のように定速上昇法について教示
- 減速の開始まで、ゆっくりと機首上げ
- 出力を増加し、ラダーで直進を維持
- 必要に応じトリミング
- 速度計を頻繁にスキャンし、ピッチ姿勢が正しいことを確認
- 小さな速度修正には細かなピッチでの修正を使用
- 旋回傾斜計を頻繁にスキャンし、直進飛行と翼の水平を確認
- マグコンパスを参照し、正しい方位の維持を確認
- 上昇性能の確認のため、高度計と昇降計を適宜参照
- 上昇からレベルオフに移行する飛行法について教示
- 所望の高度に近づいてきたら、高度計を頻繁にスキャン
- 高度計を所望の高度で停止できるだけのピッチまで正しい見越しをもって徐々に調整
- 巡航速度まで増速する間、ピッチ情報について高度計と昇降計を注意深く監視
- 速度計を監視し、機体が巡航速度まで増速したときに巡航出力を設定
- 必要に応じトリミング
- マグコンパスを参照し、正しい方位の維持を確認
- 学生に一定速度での上昇とレベルオフの飛行法を訓練機会を付与
- 一定上昇率にて定速上昇し、速度を維持する方法について教示
- 巡航飛行中に、所定の上昇率と速度で上昇するために必要な出力設定を見積もり
- 姿勢と出力を調整し、所望の上昇速度まで減速
- 必要に応じトリミング
- 速度計を頻繁にスキャンし、必要に応じ姿勢を調整、指定の上昇速度を維持
- 昇降計を頻繁にスキャンし、必要に応じ出力を調整、指定の上昇率を維持
- 水平飛行に復帰
- 学生に上昇とレベルオフの訓練機会を付与
- 学生が計器参照時、次のような定速降下について教示
- 降下出力を設定し、ラダーで直進を維持
- 速度が低下したら、必要に応じ降下のため機首下げ
- 必要に応じトリミング
- 速度計を頻繁にスキャンし、ピッチ姿勢が正しいかどうかを判断
- 細かな速度修正には小さなピッチ修正を使用
- 旋回傾斜計を頻繁にスキャンし、機体の直進を確認
- マグコンパスを参照し、正確な方位維持を確認
- 降下性能確認のため、高度計と昇降計を適宜参照
- 次のような降下からのレベルオフ法について教示
- 所望高度に接近したら、高度計を頻繁にスキャン
- 正しい見越しをもって巡航出力に設定し、高度計を所望の高度で停止するのに十分なピッチに調整
- 高度計と昇降計を注意深く監視し、所望の高度の維持を確認
- 必要に応じトリミング
- マグコンパスを参照し、正確な方位の維持を確認
- 学生に定速で降下し、レベルオフする飛行法の訓練機会を付与
- 学生が計器参照時、次のような一定降下率での降下について教示
- 指定速度で降下するための出力設定を推定
- 降下出力を設定し、ラダーで直進を維持
- 速度が低下したら、必要に応じ降下のために機首下げ
- 必要に応じトリミング
- 速度計を頻繁にスキャンし、ピッチ姿勢が正しいかどうかを判断
- 細かな速度修正には小さなピッチ調整を使用
- 昇降計を頻繁にスキャンして、出力設定が正しいかどうかを確認
- 降下率の小さな修正には、小さな出力調整を使用
- 旋回傾斜計を頻繁にスキャンし、機体の直進を確認
- マグコンパスを参照し、正確な方位維持を確認
- 所望の高度でレベルオフ
- 学生に一定降下率の降下からのレベルオフの訓練機会を付与
- 旋回針が直接的に針路変化を、間接的にバンクを示すことについて教示
- 学生が計器参照時に、次のように1旋回率の旋回について教示
- 機体が水平飛行ができるよう正しくトリムされていることを確認
- 調和のとれたエルロンとラダーを使用し、旋回針が1旋回率を示すよう所望の方位に向け変針
- エルロンで必要なバンク角を維持
- ラダーによるアドバースヨーを防ぐことで、旋回針を1旋回率の表示に維持
- エルロンを使用し、ボールを中央に維持
- 調和のとれたエルロンとラダーを使用しロールアウト
- マグコンパスを参照し、機体の所望の方位の維持を確認
- 学生に1旋回率での旋回のほかに、1/2旋回率など他の旋回率での訓練機会を付与
- 学生が計器参照時に、次のような上昇下降を伴う旋回について教示
- 部分的計器を使用し上昇を確立
- 機体の正しいトリミングを確認
- 上昇中の1旋回率旋回について教示
- 直線飛行に復帰
- 学生に上昇旋回の訓練機会を付与
- 部分的計器を使用し降下を確立
- 機体の正しいトリミングを確認
- 降下中の1旋回率旋回について教示
- 直線飛行に復帰
- 学生に降下旋回の訓練機会を付与
- 学生が計器参照中、次のような時間計測旋回について教示
- 学生に180°旋回に必要な秒数を算出させる
- 制御力を用いて旋回にロールインする際に時間計測を開始
- 正しいスキャン法の使用について強調
- 計算した時間が経過したら、制御力を用いて旋回を終了
- 機体が正しい方位への向首を判断するには、マグコンパスを参照
- 必要に応じ方位を修正するが、小さな修正では1/2旋回率を使用
- 180°旋回後は、同じく学生に90° / 30°旋回で同プロセスを反復させる
- 学生に両方向で時間計測旋回を訓練させ、訓練旋回は180° / 90° / 30°の各方位変更で実施し、続いてより難しい計算を使用した旋回訓練を実施
- 直線飛行に復帰後、コンパスを読む前に学生に一定速度での直線飛行を維持させ、その後に直線飛行中にコンパスを読んで方位を確認させる
【限定計器飛行】マグコンパスの使用
- マグコンパスに関連する誤差
- こうした誤差を考慮してマグコンパスから精確に情報を取得する方法
- マグコンパスを読み取り方位計を設定できる
- 方位計の信頼性が低下した場合でもマグコンパスを使用して精確な方位に飛行できる
- 南北方向への旋回誤差について説明
- 誤差量はバンク角によるため、急な旋回は回避すべきであることについて説明
- 誤差量は、南北の方位が最大であり、東西の方位に向かうと徐々に小さくなることを説明
- コンパス誤差は緯度にも影響することについて説明
- 増減速によるコンパス誤差について説明
- 誤差量は、増減速率によることを説明
- 東西の方位でコンパスを精確に読み取るには、速度が一定でなければならないことを説明
- 乱気流中でも信頼できる方位情報を取得するには、いくつかのコンパスの読み取り値の平均が必要であることを説明
- この課目における最初の教示は、安定した気流での実施が最適
- 旋回誤差を教示する際は、方位計を設定し旋回中にマグコンパスと比較
- 北向きで翼を水平に維持して飛行し、コンパスを鎮静化
- 西向きに旋回すると、コンパスはすぐに反対方向すなわち東向きに転回するが、その後北向きに復帰
- 東向きに旋回すると、コンパスは西向きの旋回表示をし、その後北向きの方位に復帰
- 西向きに非常に浅いバンク角で旋回すると、コンパスは瞬間的に直進針路の維持の表示となるため、東向きの緩旋回で教示を反復
- 急旋回するとコンパスは完全に反対方向に回転する場合あり
- 南向きで翼を水平に維持して飛行し、コンパスを鎮静化
- 西向きに旋回すると、コンパスは同方向への高速回転を示すが、その後南向きの方位に復帰
- 東向きに旋回すると、コンパスは同方向への高速回転を示す
- 東西方向への旋回誤差の教示を繰り返し、南北方向への旋回誤差が東西方向では存在しないことを指導
- 東向きの方位に飛行
- 水平飛行で出力を減じて速度を下げ、南方向への旋回を示す減速誤差を表示
- 水平飛行で出力を増加して速度を上げ、北方向への旋回を示す加速誤差を表示
- 減速誤差について指導し、一定の出力で機首上げ
- 加速誤差について指導し、一定の出力で機首下げ
- 西向きの方位で前述の教示事項について反復
- 南北向きの方位で前述の教示事項を反復し、増減速誤差が南北方位には存在しないことを指導
- 一定の針路と速度を維持しつつ一定の上昇率の上昇で機体を安定
- コンパス精度は、定速で上昇しても影響を受けないことについて指摘
- 安定した降下において教示事項を反復
- 学生にマグコンパスを読む訓練機会を付与
- 増速せず直進飛行を確立
- コンパス方位を読み取り
- 一定速度で直線飛行を継続
- コンパス方位を再度読んで2つの読みを比較し、情報の信頼性について確認
- 記載のコンパス誤差の推定補正表を適用し、方位計を使用せずマグコンパス方位に旋回する訓練機会を学生に付与
【限定計器飛行】異常姿勢
計器を参照しつつ、次のような事項について指導
- 異常姿勢について認識
- 回復のため迅速かつ正確に操作
- 異常姿勢は危険な状況につながる可能性があるため、迅速かつ正確な回復操作が必要
- 異常な飛行姿勢について定義し、計器表示が何らかの形で異常な場合に、異常姿勢となる可能性を想定する必要性について説明
- 誤った操縦 / 不適切なスキャン法 / 乱気流 / 不適切なトリム / 不注意により、機体が通常範囲を超えた飛行姿勢となる可能性があることについて説明
- 使用できない計器表示に依存すると、異常姿勢に発展する可能性があることについて説明
- ジャイロ計器の制限について説明し、異常姿勢でこれらの制限を超える可能性があることについて指摘
- ジャイロ計器の故障や信頼性の欠如により、異常姿勢から回復する際に部分的計器のみしか使用できない場合があることについて説明
- パイロットが物理的な感覚ではなく計器表示を信頼する必要性について強調
- 速度計と高度計の傾向を観察し、機首位置の判断の重要性について説明
- 機体の旋回の有無の判断のために、旋回針を確認する必要性について説明
- ピッチ姿勢がほぼ水平になると、速度針の動きは止まったあと逆転し始めることについて指導し、高度針の動きが止まり、昇降計がほぼ同時にその傾向を逆転させるが、この2つの計器表示は速度計よりも信頼性が低いことについて強調
- 旋回からの回復中、旋回針が中央にあれば翼はほぼ水平であることについて説明
- 姿勢計を姿勢の参照に使用する前の信頼性確認の必要性について説明
- 学生が次の各状態からの回復要領について知っていることを確認
- 過剰な速度と高度の損失を防止するために出力を減ずる
- 調和のとれたエルロンとラダー圧を加え、旋回針とボールを中央にすることで、翼を水平にする
- エレベータ圧を加え、ピッチ姿勢を水平飛行に修正
- 出力を増加
- 失速防止のため、エレベータ圧を前方に加えて機首下げ
- 調和のとれたエルロンとラダー圧を加え、旋回針とボールを中央に配置することでバンクを修正
- 機体が再び制御可能となった後、安全高度までの上昇降下の必要について指摘
- スピンでは、旋回針によるスピン方向表示は信頼できるが、ボールによる方向情報は信頼できないことについて説明
- 次のような各状態を認識し、回復する方法について説明
- 高い機首姿勢
- バンクを伴う高い機首姿勢
- 低い機首姿勢
- バンクを伴う低い機首姿勢
- 上記の要領を適用して次のような各状態を認識し、回復
- 失速
- スピン
- スパイラル降下
- スピンの教示または訓練を実施する際、教官は機体がスピンに適合する認証の保有と、公示されたすべての制限 / 限界事項の遵守を確認
- 上記の理由は、ジャイロ計器が極端な条件下で作動不良や誤作動を生ずる可能性があるためであり、ジャイロ計器の情報の確認のため、各計器のクロスチェックの必要性を強調
- 学生に視界制限装置を使用させる前に、まずは各異常姿勢から目視で回復する方法について教示
- まずはピッチとバンクの小さなエラーの回復から開始し、この基本的技法の習得後に実際の異常姿勢へと移行
- 視界制限装置を使用すると、学生は飛行機酔いを生じやすくなるため、その兆候に注意
- 速度の過度な上昇を避けるにはスパイラル降下から素早く回復が必要であるため、低速で開始すれば、学生が状況認識して回復するのに時間を掛けることができ、かつ教官の補助が必要と判断するまでの時間が得られる
- 失速 / スピン / スパイラル降下からの回復には、計器飛行状態でも有視界飛行と同じ制御入力が必要であることを指導し、新しい姿勢に移行する前には学生に同種の異常姿勢からの回復について数回訓練機会を付与
- 学生の訓練中、機体に過度な負荷がかかる可能性に注意
- 学生が全計器を使用して異常姿勢からの回復を訓練する前に、姿勢計と方位計の使用可能性について事前確認
- 「重要予備知識」の項にて概説される手順を使用して回復する方法について教示
- 計器のみを参照した異常姿勢から回復について、全計器を使用して実施させた後に部分計器を使用して反復
【限定計器飛行】無線航法
外部を参照しつつ、次のような事項について指導
- 自機位置を決定するためのVOR / ADF / GPS機器の使用法
- VOR / ADF / GPSを使用した基本的な方向決めとトラッキング
- 機位把握のために無線援助機器を使用することができれば、目視航法の援助となり、顕著な物標に乏しい地形や夜間での飛行にも活用可能
- 無線援助機器は、場外飛行における航法精度の向上とパイロットの負荷軽減に貢献
- 次のようなVOR無線局に関する事項について説明
- 無線局と信号特性
- 周波数の範囲
- 機上VOR機器について説明
- 受信機
- 表示計器
- アンテナ
- VORの利点について概説
- 干渉の回避
- 精度
- 風に対する偏流修正の容易性
- 制限事項と起こり得る誤差について説明
- 受信範囲
- 見通し線内の限界
- 航空図とカナダ飛行情報補足誌の参照法について指導
- 無線局の識別目的について説明
- 周波数の選局 / 無線局の識別 / 機器の正しい作動確認法について説明
- VORは位置に対応する機能であり、方位に対応する機能でないことについて説明
- 機体の方位線判断法と、位置交点のプロット法について説明
- 次の事項について説明
- 無線局へのラジアル・トラッキング
- 風に対する偏流修正
- 無線局の通過時の表示
- 無線局からのラジアル・トラッキング
- 所定のラジアルへの会合と、無線局への飛行法について次のとおり説明
- VORを選局して識別
- 所望のラジアルに会合後、使用するインバウンドトラックを決定し、全方位選定器 (OBS) で対応する方位を設定
- TO-FROM表示を確認
- FROMの場合、現在地から所望のラジアルへの容易な会合は不可
- TOの場合、会合に向けた飛行を継続
- コース偏位表示器 (CDI) を確認
- コース偏位が左であれば、OBSから90°を引いて会合針路を決定
- コース偏位が右であれば、OBSに90°を足して会合針路を決定
- CDIが小さくなり始めるまで、会合針路で飛行
- この段階で、会合交角を小さくしていく
- CDIが中央となり無線局に向けトラッキングできるように、インバウンド方位に旋回
- 所定のラジアルへの会合と、無線局からアウトバウンドで飛行する同様の方法について説明
- VOR課目の開始前に、VOR機器の選局と点検、無線局の識別の完了を確認
- VOR手順実施前に、方位計が正しく設定されていることを確認
- VORを使用して自機位置を決定したら、航空図の参照と地形物標を用いて視覚的に確認
- 会合するVORラジアルは、効果的な教示ができるように十分距離をもって離れつつも会合までの時間が掛かりすぎないものを選定
- 「重要予備知識」に記載されるVORの会合の基本法を活用し、最初の教示の際は、集中力や計算時間を考慮しできるだけ簡単な会合法を使用すべきであるが、基本的な手順の習得後は、必要に応じて会合交角を変更可能したり、複雑な計算が必要な方法を導入
- 学生は、初回の訓練時とその次の間で重要な事項を忘れることがあるため、VORの各訓練前に、手順を徹底的に確認
- コース偏位表示器は、必ずしもOBSで選択したラジアルを指すとは限らないことに注意
- 無線局付近でラジアルのアウトバウンドに会合する際は、浅い会合角を使用
- 次の要領について教示
- VOR受信器を選局して点検し、無線局を識別
- 機体がどのラジアル上を飛行しているかを判定
- 2つ以上の無線局からのラジアルを使用し、交点位置をプロット
- ラジアルをトラッキング
- 無線局に直行して飛行
- 所定のラジアルに会合し、無線局に向け飛行
- コース偏位表示器と中間表示 (赤縞) によって無線局の通過を識別
- ラジアルに沿ってアウトバウンドに会合しトラッキング
- 教示直後に、学生にこれらのVOR課目の各訓練機会を付与
- 次のような無指向性無線標識 (ADF) に関する事項について説明
- 無線局と信号特性
- 周波数の範囲
- 機上ADF機器について説明
- 受信機
- 表示針
- アンテナ
- ADFの利点について概説
- 低高度における受信範囲
- 信号源の見通し範囲外での受信
- 考えられる誤差や制限事項について説明
- 受信範囲
- バンク誤差
- 雷雨または磁気干渉による誤差
- 航空図とカナダ航空情報補足誌の参照法について指導
- 無線局の識別目的について説明
- 周波数の変更法について説明し、無線局を識別し、機器が正しく動作することを確認
- ADFは方位を探知する機能であることを説明
- 針路角の増加に伴って相対方位が減少し、その逆も同様であることについて説明
- 方位線に会合したり、無線局の横を通過する際に、ADFの針が機体後方に向かって移動することについて説明
- 次の公式について確認
磁針路 + 相対方位 = 無線局に向かうための磁方位
- 次の事項について説明
- 地図上への位置線のプロット法
- 地図上への交点位置のプロット法
- 次の事項について説明
- 無線局への飛行
- 無線局までの直行トラッキング
- 無線局通過時の表示
- 無線局から離隔方向のトラッキング
- 無線局に向けインバウンド・トラッキングする会合法について説明
- ADFの選局 / 識別 / 点検
- 所望の航跡と平行に旋回
- 平行な針路から、ADFの針の方向へ90°旋回
- 針が翼端位置となる相対方位が090°もしくは270°に移動したら、所望の方位へインバウンド旋回
- 上記と同様の方法で、無線局からのアウトバウンド会合法について説明
- ADF課目の開始前に、ADF機器の選局と点検、無線局の識別の完了を確認
また、タクシー中の計器点検中に、正しい検知を点検 - ADF手順実施前に、方位計が正しく設定されていることを確認
- ADFを使用して自機位置を決定後、航空図と地形目標を参照して視覚的に確認
- 会合するADFラジアルは、効果的な教示ができるように十分距離をもって離れつつも会合までの時間が掛かりすぎないものを選定
- 「重要予備知識」に記載されるADFの会合の基本法を活用し、最初の教示の際は、集中力や計算時間を考慮しできるだけ簡単な会合法を使用すべきであるが、基本的な手順の習得後は、必要に応じて会合交角を変更可能したり、複雑な計算が必要な方法を導入
※ 基本手順で示される会合交角を変更すると、所望の航跡への会合と異なる相対方位となることを学生に指導 - 学生は、初回の訓練時とその次の間で重要な事項を忘れることがあるため、ADFの各訓練前に、手順を徹底的に確認
- 風による偏流を考慮して行うADFトラッキングは、風の偏流を修正しつつ地形目標に向かう飛行と比較する必要あり
- 無線局付近でアウトバウンド方位に会合する際は、浅い会合角を使用
- 地図上に交点位置をプロットする際に起こり得るエラーは、磁差を考慮に入れないこと
- 次の事項について教示
- ADF受信器の選局 / 点検法と無線局の識別法
- 無線局からの自機位置の磁方位の確認法
- 2つ以上の無線局からの方位を使用した地図上に交点位置のプロット法
- ADFが無線局に選局されている際に、機首方位が変化すると、ADFの針も同じ量だけ変化
- 現在位置から無線局に向け直行飛行
- 偏流を排除するためのトラッキング
- 所定の方位に会合して無線局まで飛行する方法
- 機体が無線局に接近する際のADFの針の表示
- 機体が無線局を通過するときのADFの針の表示
- 無線局から離れる方向のトラッキング
- 無線局からのアウトバウンドの所定の方位に会合する方法
- 各ADF課目の教示直後に、学生に上記の訓練機会を付与
- GPSに関する次のような事項について説明
- システム概要
- 衛星の数
- 対象覆域
- 機上GPS装置について説明
- 受信機
- データベース
- 表示器
- アンテナ
- GPSの利点について概説
- 精度
- 対地速度と到着予定時刻の決定が容易
- 航跡の表示
- 起こり得るエラーや制約事項について説明
- データベースのエラー
- ユーザーの入力エラー
- 衛星の使用可能性
- カナダでのGPS使用承認条件に関する情報に関するAIPの参照法について指導
- GPS受信器の各種モードの機能について説明
- GPSが機体の固有装備である場合は、GPSが他の機体航法システムとどう連動するかについて説明
- GPS受信器をオンにする方法について説明
- パイロット入力による受信器の初期化の完了法について説明
- GPS受信器コントロールの操作方法について説明
- GPS受信器の飛行計画モードの機能について説明
- GPS受信器での飛行計画作成法について説明
- ウェイポイントの削除や追加による飛行計画の変更法について説明
- ユーザー定義のウェイポイント作成法について説明
- 空域アドバイザリー / 警告 / その他受信器が発出するメッセージについて説明
- GPS受信器の航法モードの機能について説明
- 可動マップ表示画面上の記号について説明
- 航法モードにおけるトラックバー感度について説明
- GPS受信器の「DIRECT TO」機能について説明
- GPS受信器データベースから適切な最寄り空港に関する情報の取得法について説明
- 飛行中に飛行計画に代替空港を追加する目的地変更の実施法について説明
- GPS受信器の故障時の適切な操作法について説明
- ほとんどのGPS製造社のマニュアルは、GPSシステムに関する重要な背景を知る上で優れた情報源となる
- GPS受信器の適切な操作にあたり、すべての航法機能の習得は不要であり、 VMCで受信器の使用に必要な機能に関する完全な知識を有していることを確認し、必要に応じ他の機能の学習を促す
- バッテリー電源や地上電力を用いて機体をシミュレーターにしたり、シミュレーションモードとするのでなく、可能であれば上空指導開始前に、受信器のシミュレーターや受信器付属のシミュレーションモードを使って各種モードや機能について指導
- 機体に恒久的に装備された受信器の場合、装備に関する説明や関連の制限事項について航空機飛行規程や補足誌を必ず確認
- 学生を機体に連れて行き、受信器 / アンテナ / 相互関連航法機器や警報表示器など、各種構成品について指導
- カナダでGPSを使用するための承認条件を説明するには、AIPの特別航空通知を使用
- 機内訓練が開始したら、こうしたシステムで特に学習曲線の初期段階におけるパイロットの注意がコクピットに引き付けられる傾向があり、教官と学生が共にGPS受信器とその機能に気を取られすぎないように注意することは重要で、頭を下げないこと
- データベースには誤りがある可能性があり、GPS位置を他の航法機器と照合
- 学生が受信器から情報を取得し最寄りの飛行場に目的地変更できる技量を身に付けたら、目的地変更が必要となる緊急事態を模擬し、GPSをプログラムして対処させ、安全が二の次となるほど、GPS機能に傾注させないよう指導
- 次の要領について教示
- 受信器の電源を入れ初期化
- GPS受信器のコントロールを操作
- フライトプランを作成
- フライトプランを変更
- ユーザー定義のウェイポイントを作成
- データベースから空港情報を取得
- インターセプトしてウェイポイントまでトラッキング
- トラックバーの感度を決定
- ウェイポイントへの「DIRECT TO」をプログラム
- 最寄りの適切な飛行場へ目的地変更
- システム不具合を認識
- 教示直後に、学生に各種GPS課目について訓練機会を付与
課目25:夜間飛行

【夜間飛行】導入
- 夜間飛行資格を取得するための訓練は、資格面だけでなく技量向上においても非常に楽しめるものであり、多少の復習は必要としても、学生は既に地上滑走 / 離着陸 / 場外飛行などを日中であればすべて実施可能な技量を有しているが、暗闇の中という新たな環境でこれらを実施する方法を学ぶ必要があり、その過程での学習事項はすべての飛行において有益である
- 正確な要件はCARに記載されるが、夜間飛行資格の訓練は同乗および単独の夜間飛行と組み合わせた一定量の計器飛行で構成され、教官にとっては単純なものから複雑なものへと、優れた指導原則に沿って訓練を編成し実施することが課題
- 資格要件を満足している場合、教官は最善の訓練の進め方の判断にかなり自由度があり、多様な学生の存在と地域の飛行状況等を考慮すると、この柔軟性は必要
2時間の訓練時間があれば、2回に分割すれば学生には滑走路や気象条件が異なり、より多くの経験が与えられるように、夜間飛行資格を取得した際に遭遇する可能性のある事項を考慮に入れて訓練を編成し、どのようなアプローチでもいいので学生の経験を豊かにするように配慮
教官も同様だが、学生も既に仕事などで日中を過ごしている可能性があるため、疲労には注意
地上訓練は夜間飛行資格の取得要件には含まれないものの、飛行課目の「重要予備知識」の項でリストアップされる項目の多くは、次に示す項目のように飛行開始前の夜間飛行の一般的な地上訓練で指導可
- 訓練プログラムの確認
夜間飛行資格の訓練概要を説明することで、学生がどうするかだけでなく、教官が学生にどうすべきことを望んでいるかを知らせることが可能 - 学生が空港についてよく知っている場合でも各配置の再確認は有意義であるため、空港の配置や灯火について説明
誘導路灯 / 滑走路末端灯 / スレッシュホールド灯 / 進入灯 / 障害灯 / 飛行場灯火 / 風向指示灯 / 進入角表示灯など、各種灯火システムの理解は重要 - 機体の電気系統について確認
学生は既に電気系統についてある程度の理解があるが、どう故障する可能性があるかを再確認し、不具合の場合に何ができるかについて理解する段階を設定 - 機体の灯火照明系統について説明
夜間飛行を無事に終えるには、利用可能な照明と、使用法やタイミングなど機体の照明に関する十分な知識が必要 - 夜間視力 / 運動感覚の錯覚 / 目の錯覚 / 随意運動 / ブラックホール効果 / ピッチアップダウン錯覚 / 疲労 / 冬季の寒冷時運航要領など、夜間飛行に適用されるヒューマンファクターについて説明
これらやその他の内容に触れる資料として、パイロット医学ヒューマンファクターガイド / 航空ヒューマンファクター基本ハンドブック / 航空ヒューマンファクター教官ガイドを参照
夜間には、ほぼ計器だけでしか姿勢判断ができない場合もあるため、ある程度の計器飛行が必要であり、自家用操縦士免許取得の訓練では5時間の同乗計器飛行が必要になるため、学生が何年も前にPPL訓練を完了していない限り、これだけの飛行時間は必要
多くの教官は、この計器時間の一部を夜間に実施するが、資格取得に必要な5時間の同乗夜間飛行時間の一部としては加算不可
装備的に利用可能であれば、自家用操縦士免許に必要というよりも、VOR / ADF / GPSの使用におよる機位判定 / 無線施設 / ウェイポイントへの飛行機能など、航法無線援助についてさらに学ぶことが推奨
夜間飛行証明の取得には飛行検定は不要だが、教官は学生が資格範囲の実行能力があることを見極める必要があり、これは単に必要となる同乗や単独飛行時間を実施するだけではなく、夜間飛行の訓練範囲の各課目について、飛行検定標準や自家用及び事業用操縦士免許のガイドに定められるものと同等の基準を満足する必要あり
飛行訓練
【夜間飛行】飛行前点検
- 夜間の飛行前点検について徹底的に実施する方法を指導
- 徹底的な飛行前点検は常に重要であるが、機体の照明などの点検項目が増えたり暗闇でさらに実施が困難となるため、見逃しのないように細心の注意が必要
- 日中に通常実施する飛行前点検について再確認
- 機体の電気系統について確認
- 点検中に不具合項目が発見された場合に実施する対応について確認
- 機体照明の操作法や点検法について説明
- 機内灯
- 着陸灯
- 地上灯
- 衝突防止灯
- ストロボ灯
- 航法灯
- 適切な種類のスペアヒューズの携帯の重要性について説明
- 使用可能な懐中電灯の必要性について説明
- 牽引バー / チョーク / コントロールロック / ピトーカバーの点検時は特に注意が必要であることについて説明
- 飛行前点検の最初の教示は、日中もしくは照明付き格納庫内で実施
- 日中には容易に確認できる項目も、暗闇の中では困難となる可能性があるため、細部についてより多くの注意が必要となることについて指導
- 夜間に電気系統を適切に機能させる重要性について強調
- 夜間の飛行前点検実施法について教示
【夜間飛行】エンジン始動と試運転
- 夜間における航空機の始動と試運転の実施について指導
- 夜間に実施するエンジン始動や試運転の日中との主な違いは、機内照明を正しく使用する必要があることと、暗闇のために手順に特別な注意を払う必要があること
- エンジン始動と試運転要領について確認
- エンジン始動中に発生する可能性のある緊急事態について確認
- 乗客の安全ブリーフィングについて確認
- 次の事項について説明
- コクピット照明の使用
- 懐中電灯の使用
- 紙のチェックリストの重要性と使用
- 発電機やオルタネーターの出力監視の重要性
- 学生がすべての重要なスイッチを触れるだけで発見できることを確認
- エンジン始動前は周囲の人を徹底的に見張りし、衝突防止灯と航法灯を点灯し、必要に応じ「クリア」を発声することで、エンジン始動の意図を周囲の人に警告
- 夜間はエンジン始動や試運転に時間を要し、緊張することもあるため、急がないよう注意
- 夜間に機体が意図せず前進しているかの判断は困難であるため、ブレーキが確実に効いていることを確認
- 氷 / 人 / 他機などは夜間に視認困難なため、試運転に向け移動する際は注意
- 夜間の機体始動要領について教示
- 夜間の試運転要領について教示
【夜間飛行】地上滑走(タクシー)
- 夜間の正しい地上滑走法について指導
- 暗闇でかつ通常の視覚的参照がないため、夜間の地上滑走には特に注意
- 強風状態における旋回中の計器点検や操縦装置の設定など、地上滑走要領について確認
- 有効滑走路の判断法について確認
- 次の各飛行場灯火について説明
- 飛行場灯台
- 誘導路灯
- 使用不可区域の標識
- 進入灯
- 滑走路灯
- 風向指示灯
- タクシーラインの使用
- 滑走路離脱の標識
- 蛍光の標識
- 夜間の地上滑走速度の判断法について説明
- 地上における滑走灯や着陸灯の正しい操作について説明
- 衝突防止灯と航法灯の常時使用について説明
- 投光照明区域で地上滑走する際、影で障害物の視認が困難になる可能性があるため、特に注意が必要であることについて説明
- 見張りが疎かになるほどコクピット内の作業に集中しないように夜間は特に注意が必要
- 地上滑走灯の有り無し両方の条件で地上滑走を実施させ、不慣れな区域や混雑した場所での旋回や操作時には、滑走灯の使用を推奨
- 風向を判断して記憶させ、適切な制御入力を適用した修正を実施
- 可能であれば、管制塔などより高い視点から空港全体を学生に見学させる機会を付与
- 次の事項について確認
- ブレーキ点検
- タクシー中の操縦装置の使用
- タクシー中の計器点検
- 次の事項について教示
- 滑走灯の点灯 / 消灯の両条件における夜間の地上滑走
- 地上滑走速度の判定
- 地上滑走中の着陸灯とストロボ灯の節度ある使用
【夜間飛行】離陸
- 着陸灯の点灯 / 消灯によらず、各種条件下における夜間の離陸法について指導
- 離陸時の視覚参照の違いや初期上昇中の参照がないことは、夜間離陸をするパイロットにとって特異な要求が課せられること
- 離陸前点検を含む通常 / 横風の離陸手順について確認
- 該当する緊急手順について確認
- 離陸のための着陸灯の使用について説明
- 離陸後に計器参照が必要となる場合があることについて説明
- 離陸後の上昇率を正方向に維持することの重要性について説明
- 線形加速の錯覚 (ピッチアップ錯覚) とブラックホール効果について説明
- 安全高度以下で旋回してはならないことについて説明
- 着陸灯を点灯状態で最初の離陸を実施
- 学生が着陸灯スイッチの位置を把握していることを確認
- 夕暮れ時に最初の夜間離陸を実施すると、次第に暗闇に入ることを体験可能
- 風 / 滑走路表面 / 障害物 / 乱気流 / 翼端渦などを考慮した離陸計画の重要性について強調
- 離陸が着陸灯の有無にかかわらず実施できることを確認
- 離陸を異なる滑走路、可能であれば異なる空港から実施
- 昇降計 / 高度計を使用し離陸後の上昇率が正であることを確認
- 着陸灯の有無によらず、通常 / 横風時の離陸について教示し訓練機会を付与
【夜間飛行】場周飛行
- 夜間の正確な場周経路の離脱 / 会合 / 飛行法について指導
- 夜間に正確な場周経路を飛行するには、滑走路や他機に対する正しい位置を維持するため、目視と計器を組み合わせて参照する必要があり、この精度の達成は必要かつ十分なものであり、全体の飛行技量にとって有益である
- 場周経路の飛行要領について確認
- 出発
- 進入
- 管制 / 非管制飛行場
- 無線要領
- エンジン故障 / 不時着陸 / 電気火災 / 電気不具合 / ARCALを含む無線機故障など、適切な緊急処置要領について確認
- 夜間に正確な場周経路を飛行するための方位計の使用について説明
- 滑走路灯と進入灯の使用法について説明
- 夜間の距離の判定法について説明
- 初回の夜間場周経路飛行の前に、地域における短時間の夜間慣熟飛行の実施が推奨
- 夜間の偏流判定は難しい場合があるものの、正確な場周飛行を行う上で必要であるため、学生が場周経路内で偏流を認識して正しく修正できるように指導
- 夜間の場周経路における長時間の訓練は非常に疲れるため、短時間で計画
- 場周経路を一旦離脱させ再進入することは、良い訓練経験となる
- 地域内での簡単な慣熟飛行
- 場周経路飛行について教示し、学生に訓練機会を付与
- 各種進入と滑走路の灯火条件
- 可能であれば、管制空港と非管制空港などの各種空港において訓練
- エンジン故障 / 不時着陸 / 電気故障 / 場周経路内での通信機故障などの緊急処置要領
- 正確な場周経路を飛行するための方位計の使用法について教示
- 可能であればARCAL灯火システムの使用法について教示
【夜間飛行】進入と着陸
- 夜間の効果的な進入着陸法について指導
- 夜間進入で使用する視覚参照物は、日中に使用するものとは別物
- 発生可能性のある各種錯覚により、夜間の進入着陸における特別な要求が課される
- 次の事項について確認
- 適切な点検を含む通常及び横風での進入と着陸
- 着陸復行要領
- 進入灯と滑走路灯
- VASISとPAPI
- 後方乱気流の回避
- ARCAL要領
- 蛍光標識の使用
- 進入と着陸に関連する錯覚について説明
- 滑走路勾配と滑走路幅
- 無灯火の地形に進入する際のブラックホール効果
- フレアを判断する際の滑走路灯の高さや輝度の影響
- 進入角と偏流を判定するための滑走路灯の使用について説明
- 着陸の際に着陸灯を使用することの利点と欠点について説明
- 着陸フレア中の出力の使用について説明
- 滑走路離脱前の減速の重要性について説明
- 夜間飛行への段階的な移行のため、初回の夜間進入着陸を薄暮の間に実施することを検討
- 適切なトリムと速度管制の重要性について強調
- 学生に当初数回の着陸で着陸灯を使用させ、次に消灯して着陸を数回実施させる
- 滑走路に対する機体前方 / 垂直方向 / 横方向の動きを確認するために、着陸時に学生が十分に前方を見ていることを確認
- 中央に設置された着陸灯の光線は縦軸の延長であり、横風着陸の際に滑走路との正しい軸線の調整を支援するために使用可能
- フルストップ着陸は、ストップ&ゴーまたはタッチ&ゴーを試行する際の夜間訓練の導入部分として有益
- 教示し、学生に訓練機会を付与
- 夜間の進入着陸のいて、横風 / 各種滑走路 / 着陸灯消灯 / VASISやPAPI消灯 / 各種滑走路灯輝度など、バリエーションを徐々に導入
- 直線進入
- コクピットの計器照明故障 / 着陸灯または無線機故障などの模擬システム故障
- フレア時の出力の使用
- 着陸復行
- 夜間の進入と着陸で経験する可能性のある錯覚について指導
【夜間飛行】パイロット航法
- 夜間の効果的なパイロット航法技術について指導
- 昼間と同様、夜間のパイロット航法は複雑であり、灯火のある地形物標に頼る必要性 / 航法の参照に利用可能な詳細の相対的な欠如 / 夜間の天候変化の推察が困難であることは、パイロットに対し特別な要求を課すものの、うまくいけば非常に有益な作業となる
- 次の事項について確認
- 飛行前計画要領
- 出発 / 巡航 / 到着のパイロット航法技術
- コクピット内照明
- 緊急処置要領
- ATC支援やDFステアの取得
- 次の事項について説明
- 正確な方位と時間管制が重要である理由
- 夜間の地図判読
- 夜間の距離判定法
- 着陸灯を利用した降水量の特定法
- 徹底的な気象ブリーフィングの必要性について強調
- 飛行計画において、法的な最小VFR飛行条件よりも高い個人的に設定した気象制限の使用を推奨
- 可能であれば、人口密集地域と過疎地域を航法できるよう飛行計画
- 各レグに常時代替案と「中止要件」を準備
- 場外飛行実施前に、学生の緊急処置要領の理解度を確認し、飛行中に「もしこうなら」のシナリオを使用し意思決定技量を体得
- 場周経路から局地空域への短距離飛行は、実際の場外飛行の実施前にパイロット航法技量を鍛えるために使用
- 可能であれば、場外飛行中に他の空港への着陸を計画
- 単独での場外飛行は必須ではないものの、多くの飛行学校では別の空港における場周飛行を含む夜間の短距離単独場外飛行の実施を推奨
- 次の事項について教示
- 地図判読
- 距離判定
- 学生の訓練を監督
- 飛行前計画
- 出発
- 針路設定
- 巡航航法
- 到着
- 緊急処置
【夜間飛行】計器飛行
- 課目24に続き、夜間飛行に必要な計器飛行法について指導
- 計器飛行が必要となる条件である暗闇の中でこの飛行技術を鍛えるため、夜間計器飛行の実施について検討
- 学生と教官の双方にとって方向感覚喪失のリスクが夜間に高まるため、異常姿勢からの回復訓練は日中に行うのが最適
- できれば夜間単独飛行を学生に実施させる前の段階で、必要な夜間の計器飛行を完了すべき
【夜間飛行】緊急手順
- 夜間の正しい緊急対処要領について指導
- 日中に発生する可能性があるすべての緊急事態は、夜間にも発生する可能性があるだけでなく、さらに複雑化したり夜間環境特有の緊急事態もあり、また実際に発生もしていることから、学生はこれらの緊急事態について理解し、迅速で適切な対処要領を実施する能力が必要で、決断にかかる時間は非常に重要
- 次の事項について確認
- POHやFTMによるすべての緊急処置要領
- DFステア要領
- 燃料系統
- 電気系統
- 次の事項について説明
- 電流計の読み取り方
- 過充電や過少充電の影響
- 電気的故障が発生した場合の対処
- 適切なタイプのスペアヒューズ携帯の重要性
- 手探りでヒューズを見つけ交換する方法
- ためらったり見ることなく、コクピット内の重要なスイッチやコントロールを見つけられることの重要性
- コクピット照明の故障が発生した場合の懐中電灯の使用
- 手探りでELTを見つけてオンにする方法
- 地形 / 積雪 / 月明かり / 高速道路上の自動車の照明などを考慮した夜間の不時着離場の選択法について説明
- 不時着陸時の着陸灯の使用について説明
- ARCAL操作と関連する通信機故障について説明
- 夜間の緊急事態に対処する上で、燃料系統や電気系統に関する知識が非常に重要である理由について説明
- 緊急対処要領について指導する際は、「事故の訓練」とならないように飛行上のリスクに配慮
- 訓練の緊急事態対処では「模擬」の用語を必ず使用
- 次のような想定の緊急事態について教示し、学生に実施機会を付与
- コクピット照明故障
- 電気系統故障
- 夜間のNORDO手順
- 場周経路内での不時着陸要領
- 不時着陸地の選定
- 学生が重要なスイッチをすべて手で位置確認できることを確認
課目26:水上機

水上機に関する教官ガイドは別で定められている
Instructor Guide – Seaplane Rating” (TP 12668E).
課目27:雪上機

- 雪上機の飛行運用における慣熟
- 必要に応じて実施
- 一般に使用されるスキーの種類について話し合い
- ホイールシャフトに取り付ける標準タイプのスキー
- 車輪スキー複合型
- その他
- 飛行前の目視点検で使用する点検用の追加装備
- ケーブル / ショックコード / 留め具 / スキーピストンなど、雪上機のみにある重要な飛行前点検項目について確認
- タクシーに関する考慮事項について説明
- クリアな氷を破壊して進む雪上滑走法
- スキーへの付着の原因となる可能性が最も高い雪の状態
- ホイールスキーの駐機や運用におけるスキーに付着する土や泥 / 氷などの危険性
- 一部の表面状態におけるブレーキ機能の低下
- 滑走中にエンジン過熱に至る可能性のある条件
- 離陸滑走開始前に、予定離陸経路上を最初に滑走し雪の圧縮が必要になる雪の条件
- スラッシュ状態での運用や回避法
- 離陸に関する次の事項について説明
- 離陸方法
- 離陸滑走長における雪の影響
- 陸上機の不整地離陸との類似点
- 高い雪の吹きだまりがあることの考慮
- 横風離陸法
- 着陸に関する次の事項について説明
- 次のような適合性判断の重要性について指導
- 予定着陸区域の地表面状況
- 引き続き離陸に利用できる滑走路長
- ホワイトアウト状態や断続的な雪などでも利用できる視覚的な参照物
- 通常の進入着陸と横風での進入と接地時の考慮事項
- 断続的な積雪 / 吹雪 / 高めの地吹雪状態などでの着陸に関する考慮事項
- 機体の凍結を防止するための着陸後の要領
- 駐機とタイダウンに関する考慮事項
- 機体の凍結防止の木材 / 枝 / プラスチックの使用
- タイダウン法
- スキー操作に関する一般的エアマンシップの考慮事項
- 泥地 / 裂け目 / 空洞 / 深い雪などの発見と回避
- 小川 / 河口などの地下流区域の回避
- 裸氷上での運航
- 横風の影響
- 秋季と春季における湖での運航中の氷の状態
- 離陸後に凍結した泥によるホイール固着
- 氷の質や厚さにおける耐荷重に関する知識
- スキー運用の性質状、翼上の着霜状態での放置、ドラム缶からの燃料給油、野外における整備などの可能性が高くなるため、更なる注意が必要
- 凪状態での水上機の運航と、ホワイトアウトや断続的吹雪状態での雪上機の運航が類似していることから、水上機の資格を有するパイロットは、陸上機パイロットよりもこうした問題に理解があることが一般的
- 雪上機による裸氷上の着陸は、十分配慮を行わないと忘れられない出来事になってしまう可能性があり、普段経験するよりも摩擦力が低下していることを理解すべく、条件が良好である限り学生にもこの状況の体験機会を付与
- 場外の雪上機の運用においては、裸氷での運用の場合を除き、選定した着陸地から離陸するのに必要な滑走長は、単に着陸で必要な距離ではなく、運用上の考慮が必要であることを強調
- 適切な人命救助装備と適切な衣服の装備は、特に計画の有無によらず場外での夜を越す滞在の際には不可欠
学生は、氷結したエンジンの対処と始動に関する問題と、乗客に対する責任を理解
- 機外点検
- 雪上機に関する追加の考慮事項を指摘
- スキー板が表面上で氷結していないことを確認
- タクシー要領について教示
- 陸上機と比較して機体運動における制御力が低下するため、フラップ上げ / ステアリングのための操縦桿の前方への押し込み / 狭小区域にける旋回時の尾部のロープ使用 / 積雪部回避のための十分な間隔の確保などといった方法を適用
- 深い雪や裸氷など各種地表面状態で、機体を動かし続けるためには大きなエンジン出力変化が必要
- 機体を停止した際の凍結防止法
- 離陸要領について教示
- 駐機場を出発前に次の事項を実施
- 可能な運転を確認する通常の試運転を完了
- 離陸点検を完了
- 既存の条件下における通常離陸
- 条件次第では、まず離陸表面を地上滑走してみて、積雪の圧縮状況を確認
- ホワイトアウト状態の場合や通常の目視物標が参照できない場合には、離陸法や姿勢確認のために計器使用が必要になることについて指導
- 着陸要領について教示
- 着陸表面を点検し、適しているか / 風向 / 着陸経路などを決定
- 通常の進入と着陸
- 深い雪がある場合、着陸後の地上滑走要領にしたがって固着が発生しないようにし、自力で容易に再移動ができることを確認
- 機体の完全停止前のスラッシュ (泥) 点検法
- 駐機とタイダウン
- 雪上機の追加の考慮事項について教示
課目28:型式変更

- 既存の知識や技量について、別の型式もしくはより高度な型式の機体の運航に必要なものに対して補足
- 必要に応じて実施
- POHを使用し、次の様々な要領や技法について説明
- 重量平衡と搭載負荷
- 燃料系統のシステム / 管理 / 消費 / 飛行範囲
- 補助操縦装置の使用と運用
- 該当機の脚装置の運用
- フラップ / 油圧系統 / 電気系統
- 承認 / 非承認手順の運用上の考慮事項 / ハンドブックの航空図や性能表の使用
- 緊急処置要領
- 必要に応じ重要な情報を学生に確認し、誤りがあれば訂正
- 近道で最短の指導をしたくなるが、回路をショートさせてしまうようなもので、そうした誘惑を抑えて学生が単独飛行する際に冒した失敗から学ばせる方が効果的であり、個々の要望を反映させて転換訓練を計画するため、学生の背景や能力を注意深く評価
- 型式変更では、格納式脚装置 / 定速プロペラなど、これまでに経験していない装置について指導する必要がある場合があるが、これらはより高速な装置にも通常関連付けられるため、学生の学習能力に合わせて指導の進捗を調整
- POHの情報は、多大の調査を経て製造業者が記載したものであるため、全情報への精通が求められ、また同型式でも製造年が異なる機体では速度や操作上の違いが生じることから、無視すると問題が発生する可能性があることについて指導
- その型式の経験が限定的もしくはまったくない場合には、機体に慣熟できるようにより複雑な訓練に進む前に通常の上空課目を実施
- 「チェックアウト」は、学生が最大総重量における運用を含むすべての形態で機体の特性に慣熟したら完了
- 機外点検中での根本的な点検項目の違いや追加の項目について、学生に十分に理解させる
- エンジン始動 / 暖気運転 / 試運転 / 離陸前点検を監督
- 離陸後、本格的な指導開始前に、学生が飛行特性に慣熟するのに十分な時間を与えるため水平飛行を実施
- 学生が通常の飛行操作 / 失速 / 急旋回などを実施して航空機に慣熟したところで、離着陸訓練のため場周経路に帰投
- 学生が十分な技量に到達後に必要に応じ訓練を付与
- 必要に応じ機体のエンジン停止と駐機要領について監督
課目29:緊急手順

- 緊急事態やシステム不具合時にまずそれを認識をし、POHにしたがったすべての手順を完了法について指導
- 異常または危険な状態が確認された場合、パイロットは状況を正しく評価し、問題を解決するための適切な手順を実施するが、システム不具合に完全に対処できない場合には、代替行動の検討も必要であり、場合によっては近隣の代替空港への目的地変更も検討
- 意思決定の考え方と緊急事態時の処理要領について確認
- 使用する機体に関し次の要領について説明
- 地上でのエンジン火災
- 飛行中のエンジン火災
- 油圧低下
- フラップ故障 (スプリット状態)
- 燃料系統 (計量器 / タンク切替器 / 加圧器)
- 電気系統不具合
- 電気火災や発煙
- ハッチ / パネル / ドアの上空での不完全閉鎖
- 客室火災
- 不時着水
- その他各機固有の系統故障
- 緊急事態やシステム不具合の発生を企図する前に、学生が通常手順に習熟しており機体を十分に取り扱えることを確認
- 学生は、すべての緊急チェックリスト / システム / 緊急手順を含む、POHの様式に習熟していることが重要であり、教官は学生がメモリー項目の理解を確認
- 緊急手順は、訓練の後半段階だけでなく、段階的に導入する必要があり、特にフラップ / 電気系統 / 燃料系統の問題を伴う状況は、訓練の初期段階から指導
- シナリオを付与して緊急要領について指導することで、学生は問題を分析し、実際の状況に備えられるようになり、常に健全な意思決定能力が鍛えられる
- 学生の欲求不満や知識や技術習得の効果を考慮し、緊急事態のシナリオは合理的かつ現実的なものとして緊急事態の複合的発生を避け、学生に過負荷とならないように注意
- 訓練に使用する機体で有効となる対処手順は、検定官により確認される可能性があるため、訓練修了時にすべての緊急手順やシステム不具合の対処手順の理解度を確認
- 機種固有の全緊急事態およびシステム故障の対処要領は、POHにしたがって指導
- シナリオを活用して何が起こり得るかを可視化しつつ緊急事態の対処法について学生と検討
- 機内で学生と一緒に、各項目を大声でコールし、各種操作を実際に行って対処手順の訓練を実施
- 学生は全緊急処置チェックリスト項目がどこに書かれているかについて知っている必要があるため、メモリー項目について学生に質問